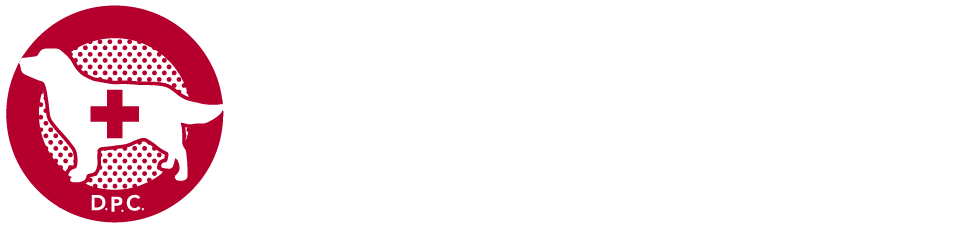犬の皮膚や口内に現れる扁平上皮癌|早期発見と治療のポイント
愛犬の健康を守るために、気をつけたい病気のひとつが扁平上皮癌です。この病気は皮膚や粘膜にできる悪性腫瘍(がん)の一種で、特に口の中や皮膚、指先などに現れることがあります。
治療の基本は手術ですが、場合によっては放射線治療や化学療法、緩和ケアが選択されることもあります。ただし、病状が進行すると治療の負担が大きくなるため、できるだけ早く見つけることが何よりも大切です。
そのためには、日頃の健康チェックや定期的な健康診断が欠かせません。
今回は、犬の扁平上皮癌の特徴や早期発見のポイント、治療の選択肢について解説します。

目次
扁平上皮癌とは?
扁平上皮癌とは、皮膚や粘膜を構成する扁平上皮組織に発生する悪性腫瘍(がん)の一種です。猫の口内にできることが多いとされていますが、犬でも比較的よく見られる腫瘍のひとつです。
このがんは局所浸潤性が高い(がん細胞が周囲の組織に広がりやすい)ものの、遠隔転移(肺や肝臓など別の臓器へ転移すること)のリスクは比較的低いといわれています。
猫では鼻の中や口内に発生しやすいですが、犬の場合は口内だけでなく、腹部や体幹の皮膚、指先、鼻の表面などにも現れることがあります。
また、犬の口内には悪性黒色腫(メラノーマ)、皮膚には肥満細胞腫が最も多いとされています。これらの腫瘍は扁平上皮癌とは異なる特徴を持っています。
・悪性黒色腫(メラノーマ):メラニンという色素細胞に由来するため、黒っぽく見えることが多い(ただし、黒くならないタイプも存在)。
・肥満細胞腫:皮膚に刺激が加わると、しこり周辺が赤く腫れる「ダリエ徴候」という反応が見られる。
扁平上皮癌の発症リスクを高める要因
扁平上皮癌の発症には、遺伝や加齢、紫外線の影響、環境要因などが関与していると考えられています。
◆遺伝
プードル、ダルメシアン、ビーグルなど、一部の犬種では発症リスクが高いことが知られています。
◆加齢
特に10歳以上の中高齢の犬で多く見られます。
◆紫外線の影響
毛色が白く、毛が短い犬(ブルテリアなど)は紫外線の影響を受けやすく、発症リスクが高まるといわれています。
◆環境要因
猫では、タバコの煙やノミ避けの首輪が発症リスクを高める可能性があるとの報告もあります。犬に関する具体的なデータは少ないものの、受動喫煙や有害な化学物質への暴露は健康リスクとなる可能性があるため、注意が必要です。
症状と発見のポイント
扁平上皮癌は発生する部位によって症状が異なります。 口内や皮膚、指先など、どこにできるかによって愛犬の様子が変わるため、普段から注意深く観察することが大切です。
<口内にできた場合>
初期にはよだれの量が増える、食べづらそうにする、歯茎から出血するといった症状が現れることがあります。これらの変化は口内の違和感や痛みが原因で起こることが多く、食欲の低下につながることもあります。
さらに、腫瘍が進行すると顎の骨にまで広がり、顔の形が変わったり、骨がもろくなって骨折したりするケースもあります。
<指先にできた場合>
歩くのを嫌がったり、足を引きずったりする仕草を見せることがあります。また、違和感や痛みを感じて、しこりを気にして頻繁になめたり、噛んだりすることも特徴的な症状です。
<皮膚にできた場合>
皮膚表面に発生すると、しこりが大きく腫れ、表面の毛が抜けることがあります。また、しこりがただれたり、出血したり、潰瘍(皮膚や粘膜が深く傷ついた状態)ができることも特徴的です。
指先や皮膚にできた腫瘍は目で見て確認しやすいため、しこりがないかこまめにチェックすることで早期発見につながります。
しかし、口内にできた場合は気づきにくいことが多く、症状が出ても歯周病などの別の病気と勘違いしてしまうケースも少なくありません。そのため、愛犬のよだれの量や食べ方、口臭の変化に注意することが大切です。
診断方法
扁平上皮癌が疑われる場合、まずは視診と触診でしこりの状態を確認します。そのうえで、より詳しい検査が必要な場合には、以下のような方法が実施されます。
◆細胞診や生検(病理検査)
・細胞診:しこりに細い針を刺して細胞を採取し、顕微鏡で調べます。
・生検:しこりの一部または全部を切り取り、詳しく分析します。
この検査によって、腫瘍の種類や悪性・良性の判断が可能になり、治療方針を決める際の重要な手がかりとなります。
◆画像検査(X線、CTなど)
・X線(レントゲン):骨への浸潤や肺などへの転移がないかを確認します。
・CT検査:より詳細な画像を撮影し、腫瘍の広がりや転移の有無を調べます。特に手術の際にどこまで切除すべきかを判断するのに役立つ検査です。
<病期(ステージ)の分類>
検査結果をもとに、腫瘍の大きさ、リンパ節への転移の有無、遠隔転移の有無を確かめることで、扁平上皮癌を1〜4のグレードに分類します。
グレードが高くなるほど進行しており、治療の方針や予後(病気の経過の見通し)を判断する際の目安となります。
治療
治療法は、腫瘍ができた部位や進行度(グレード)によって異なります。主な治療方法として、外科手術、放射線治療、化学療法、緩和ケアがあります。
<外科的治療(手術)>
扁平上皮癌の治療で最もよく選ばれる方法です。特に皮膚や指先にできた場合は、腫瘍を取り除くことで治療できることが多く、早期に発見できれば手術のみで完治を目指せる可能性があります。
しかし、口内にできた場合は、腫瘍の広がりによって顎の骨ごと切除する手術が必要になることもあり、犬への負担が大きくなるケースがあります。食事の仕方や生活の質(QOL)に影響を及ぼすこともあるため、治療後のケアについても獣医師としっかり相談することが大切です。
<放射線治療>
放射線治療は、鼻の中など手術が難しい部位に腫瘍ができた場合に適用されます。また、手術後の補助治療として用いられることもあります。
ただし、治療費が高額になりやすいことに加え、放射線治療を実施できる動物病院が限られているという課題があります。また、治療期間中は頻繁な通院が必要になるため、飼い主様と愛犬の負担も考慮しながら、慎重に治療方針を決めることが大切です。
<化学療法(抗がん剤治療)>
化学療法は、単独では大きな効果を発揮しにくいため、手術や放射線治療と組み合わせて用いられることが一般的です。
特に、最近では「トセラニブ」という分子標的薬が犬の扁平上皮癌に効果が期待できるといわれており、治療の選択肢のひとつとして注目されています。
ただし、すべての症例で効果があるわけではなく、副作用のリスクも伴うため、獣医師と十分に相談しながら治療方針を決めることが重要です。
<緩和ケア(QOLを維持する治療)>
根治が難しい場合でも、愛犬ができるだけ快適に過ごせるようにQOL(生活の質)を維持することが大切です。そのために、以下のようなケアが行われます。
・痛みを抑える薬の投与(鎮痛剤や抗炎症剤など)
・腫瘍の一部を縮小する治療(負担の少ない処置を選択)
・皮膚表面のケア(傷口の保護や感染予防)
緩和ケアは、愛犬の負担を減らしながら穏やかに過ごせるようにサポートする治療です。飼い主様と獣医師が相談しながら、愛犬にとって最適な方法を選んでいくことが大切です。
治療後のケア
扁平上皮癌は治療後のケアがとても重要です。特に口内に発生した場合、広範囲の切除が必要になることが多く、術後の食事管理や傷口のケアが欠かせません。
<口内にできた場合>
腫瘍の広がりによっては、顎の骨を広範囲に切除する手術が必要になることがあり、その場合、術後の食事管理が重要になります。特に、自力での食事が難しい場合は、胃瘻(いろう)チューブを使用して栄養を補給することもあります。
胃瘻チューブを使用する際は、適切なケアが欠かせません。チューブが詰まらないようにこまめに洗浄し、装着部位の皮膚を清潔に保つことで、感染を防ぐことが大切です。また、皮膚に炎症が起きないよう、獣医師の指示に従いながら丁寧に管理することが求められます。
チューブが外れた後の食事も工夫が必要です。愛犬の負担を軽減するため、柔らかいフードや流動食を取り入れると食べやすくなります。また、食事の形状や水分量を調整しながら、愛犬の様子を見て無理のない範囲で進めていくことが大切です。
<皮膚や指先にできた場合>
術後の傷口はデリケートな状態のため、適切な保護とケアが欠かせません。愛犬が傷をなめたり引っかいたりすると傷の治りが遅くなり、感染のリスクが高まることがあります。そのため、エリザベスカラーや包帯を使用して患部を守ることが推奨されます。
また、手術後の傷口は細菌感染を起こしやすいため、獣医師の指示に従いながら、適切な消毒や処置を行うことが大切です。傷の状態をこまめにチェックし、赤みや腫れ、異常な分泌物が見られた場合は、すぐに動物病院に相談するようにしましょう。
予防
扁平上皮癌の予防には、日常的なケアがとても大切です。
特に、日焼け対策や皮膚・口内のチェックを習慣にすることで、リスクを軽減できます。紫外線は発症の一因と考えられているため、ラッシュガードを着せる、日差しの強い時間帯の外出を避けるなどの工夫をするとよいでしょう。
また、ご家庭でのケアに加えて、定期的に動物病院で健康診断を受けることも重要です。
口内の腫瘍は飼い主様が気づきにくく、気づいたときにはすでに進行していることも少なくありません。早期発見・早期治療につなげるためにも、定期的な検査を受けることをお勧めします。
まとめ
犬の扁平上皮癌は、早期発見と早期治療が何よりも大切な病気です。皮膚や指先にしこりを見つけたら、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。
特に口内にできた腫瘍は飼い主様が気づきにくく、知らない間に進行してしまうことも少なくありません。そのため、定期的な健康診断を受けて、獣医師による専門的なチェックを受けることが大切です。
愛犬と健やかに暮らし続けるためにも、少しでも気になることがあれば、ぜひ当院までご相談ください。
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。