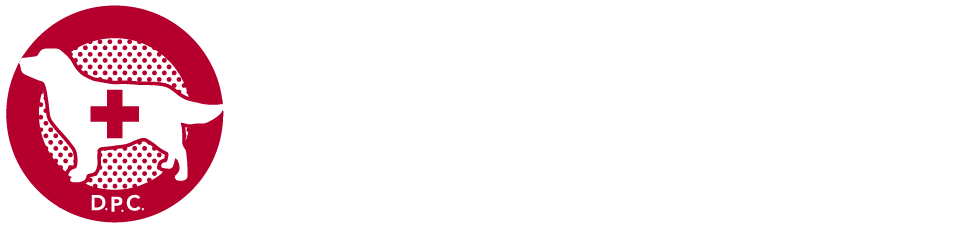成長が遅いのは病気のサインかも|門脈体循環シャントとは?
門脈体循環シャントは、特に若い犬や猫に多く見られる先天的な疾患で、発育不良や体重の伸び悩みといった見た目の変化だけでなく、けいれんや意識障害といった重い神経症状が現れることもあるため、早期発見と適切な治療が命を守るカギとなります。
今回は、門脈体循環シャントの基礎知識から主な症状、検査による診断、手術を含む治療法、そして術後のケアについて解説します。

目次
門脈体循環シャントとは?
門脈体循環シャント(PSS:Portosystemic Shunt)は、肝臓に向かう血流が異常な経路を通ってしまう病気です。
通常、犬や猫が食事から吸収した栄養や老廃物(毒素)は、「門脈」という血管を通じて肝臓へ運ばれ、解毒や代謝の処理が行われます。
ところが、門脈体循環シャントがあると、門脈の途中にシャント(異常な血管)ができてしまい、本来肝臓を通るはずの血流が、そのまま体中を巡ってしまう状態になります。
このため、毒素が解毒されずに全身に回り、さまざまな症状を引き起こすほか、栄養も十分に吸収されず、成長や発育にも悪影響が出てしまいます。
発症のタイプ|先天性と後天性
門脈体循環シャントは、発生の仕組みによって「先天性」と「後天性」に分けられます。
犬ではほとんどが先天性で、1歳未満のパピーに多く見られます。
ヨークシャー・テリアやミニチュア・シュナウザーといった小型犬種に多いことが特徴です。
一方で、なんらかの疾患により門脈圧が高い状態が長く続くと、後天的にシャントが形成されることもあります。
シャントの位置による分類|肝外性と肝内性
また、シャントができる位置によって、「肝外性」と「肝内性」にも分類されます。
<肝外性シャント>
肝臓の外にある門脈に異常があり、小型犬種で多く見られます。
<肝内性シャント>
肝臓の内部の門脈で異常が生じ、ラブラドール・レトリーバーなどの大型犬種で確認されることが多いです。
なお、門脈体循環シャントは犬に多い病気ですが、猫でもまれに発症することがあります。
猫では、肝外性シャントが多いとされており、犬と同様に早期の発見と治療が重要です。
気づくべき症状のサイン
門脈体循環シャントでは、体の中で処理されるはずの毒素が全身に回ってしまうことで、さまざまな症状が現れます。
そのため、以下のような変化に早く気づくことがとても重要です。
・体格の異常:成長が遅い、体格が小さいなど。兄弟姉妹と比べて明らかにサイズが小さい場合は注意が必要です。
・神経症状:ふらつき、けいれん、意識がぼんやりする、名前を呼んでも反応が鈍いなどの症状が見られることがあります。
・消化器症状:食欲がない、吐く、下痢をするなど。日によって波があることもあるため、「いつもと違う」が続くときは要注意です。
・尿路症状:おしっこの回数が多い、血尿が出る、結石ができやすいなど。体内のアンモニア代謝が影響している場合があります。
これらの症状は、「食後」に症状が悪化しやすいという特徴があります。
また、年齢によって現れやすい症状が異なる点にも注意が必要です。
たとえば、若い犬では神経症状が目立ちやすく、成犬になると消化器症状のほうが顕著に出るケースもあります。
診断方法
門脈体循環シャントが疑われる場合には、以下のようないくつかの検査を組み合わせて正確な診断を行います。
◆問診と身体検査
体重や体格、成長の様子などを確認するとともに、普段の食事内容や症状が現れるタイミング、持続期間などを詳しく伺います。こうした情報が診断の手がかりになります。
◆血液検査
肝臓の働きを見るための検査で、肝酵素の異常や、アンモニア濃度の上昇などが見られることがあります。特にアンモニア値は、シャントによる代謝異常を反映しやすい項目です。
◆画像診断(超音波検査、CT、MRIなど)
シャント血管の位置や走行、形態を視覚的に確認するための検査です。特に手術を計画する際に重要になります。
◆肝生検(肝臓の組織検査)
肝臓の一部を採取し、組織の状態を詳しく調べることで、肝臓にどのような変化が起きているかを確認します。
◆食事負荷試験
食前と食後のアンモニアやTBAの数値を調べることで、肝機能の評価に役立ちます。シャントの存在を示す重要な手がかりになることがあります。
これらの検査を通して、門脈体循環シャントかどうかを見極めるだけでなく、肝炎や肝臓腫瘍など他の肝疾患との鑑別も行います。
治療法
門脈体循環シャントの治療は、内科的な管理と外科的な手術の大きく2つに分かれます。
症例によって適した方法が異なるため、年齢や体格、シャントの種類、全身状態などを踏まえた判断が必要です。
<内科療法>
内科療法は、病気を根本的に治すというよりも、症状をコントロールしながら体への負担を軽減することを目的とした治療です。
肝臓病用療法食や、抗菌薬の投与などが行われます。
この方法は、特に後天性シャントや、手術のリスクが高い症例において選択されることが多いです。
<外科手術>
外科的治療は、シャント血管そのものを閉鎖し、正常な血流に戻すことを目的とした根本的な治療です。
主な方法としては、結紮術(シャント血管を縛る)や、セロハンバンド法(シャント血管にフィルムバンドを巻き付け手術後の反応でシャント血管を閉鎖させる)、アミロイドコンストリクター(ゆっくりと血管を閉じる特殊な器具)を用いる方法があります。
また近年では、より身体への負担が少ない方法として、カテーテルを使って血管内から処置を行う「血管内塞栓術」も提案されています。
これらの外科手術は、主に先天性の門脈体循環シャントに対して行われ、根治が期待できる治療法です。
治療後には、門脈高血圧症や神経症状の悪化といった合併症が起こる可能性もあるため、術後の経過観察がとても重要になります。
症状によっては急な容態の変化に備えて、緊急手術が必要となるケースもありますので、退院後も定期的なチェックが欠かせません。
術後のケアと生活管理
術後の生活管理は、その後の体調や予後にも大きく影響するため、日常の中で意識して取り組んでいきましょう。
◆食事管理の継続
手術後もしばらくは、肝臓への負担を減らすために低たんぱくの療法食を継続します。状態に応じて、フードの種類や量は獣医師と相談しながら調整していきましょう。
◆定期的な検査
血液検査や画像検査を通じて、肝機能の回復状況やシャントの再発がないかを確認します。
◆運動量と生活環境の見直し
過度な運動を避け、体への負担をできるだけ減らすことが大切です。また、静かで落ち着いた環境を整えてあげることで、ストレスの少ない生活を送ることができます。
なお、術後も肝臓の数値が完全には正常に戻らないこともありますが、合併症がなく、日常生活の中で安定して過ごせていれば、予後は良好とされるケースが多くあります。
ただし、手術前に見られていたような症状が再び現れた場合は、再発や合併症の可能性もあるため、すぐに動物病院を受診しましょう。
まとめ
門脈体循環シャントは、特に子犬や子猫の時期に見られやすい病気です。
見た目では気づきにくいケースもありますが、早期に発見し、適切な治療を受けることで、健康な生活を取り戻すことができます。
そのためにも、定期的な健康診断はとても重要です。成長段階にある子たちにとって、小さな異常を早めに見つけることが、命を守る大きな一歩になります。
大切な家族である愛犬・愛猫がこれからも元気に過ごせるように、日々の観察と健康管理を続けていきましょう。
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。
<参考文献>
Van den Bossche, L., & van Steenbeek, F. G.(2023)「Congenital portosystemic shunts in dogs and cats: Classification, pathophysiology, clinical presentation and diagnosis」*Veterinary Sciences*, 10(2), 160. https://doi.org/10.3390/vetsci10020160 (2025年2月10日閲覧)