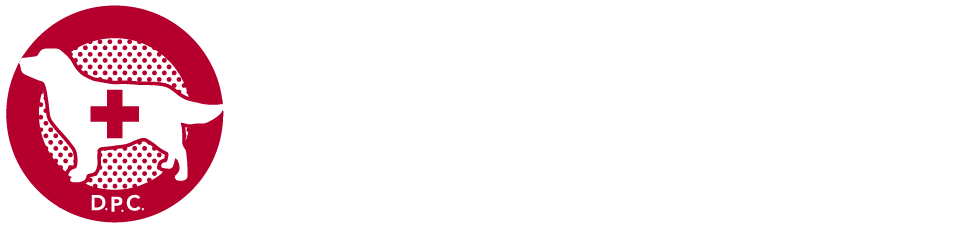犬のクッシング症候群とは?|犬の水の飲みすぎ・お腹が膨らむなど気になる症状に要注意
「最近、水をたくさん飲むようになった」「お腹がぽっこりしてきたけれど、年のせいかな?」
そんな変化を、なんとなく見過ごしていませんか?
実はそれ、クッシング症候群という病気のサインかもしれません。
この病気は、シニア犬(中高齢の犬)に多く見られ、症状がゆっくりと進行するため、老化現象と見過ごされやすいのが特徴です。
だからこそ早めに気づいて治療を始めることで、犬たちの快適な生活を守ることができます。
今回はダイゴペットクリニックの内分泌科の知見をもとに、クッシング症候群の基礎知識から日常のケアまで、獣医師の視点でわかりやすくご紹介します。
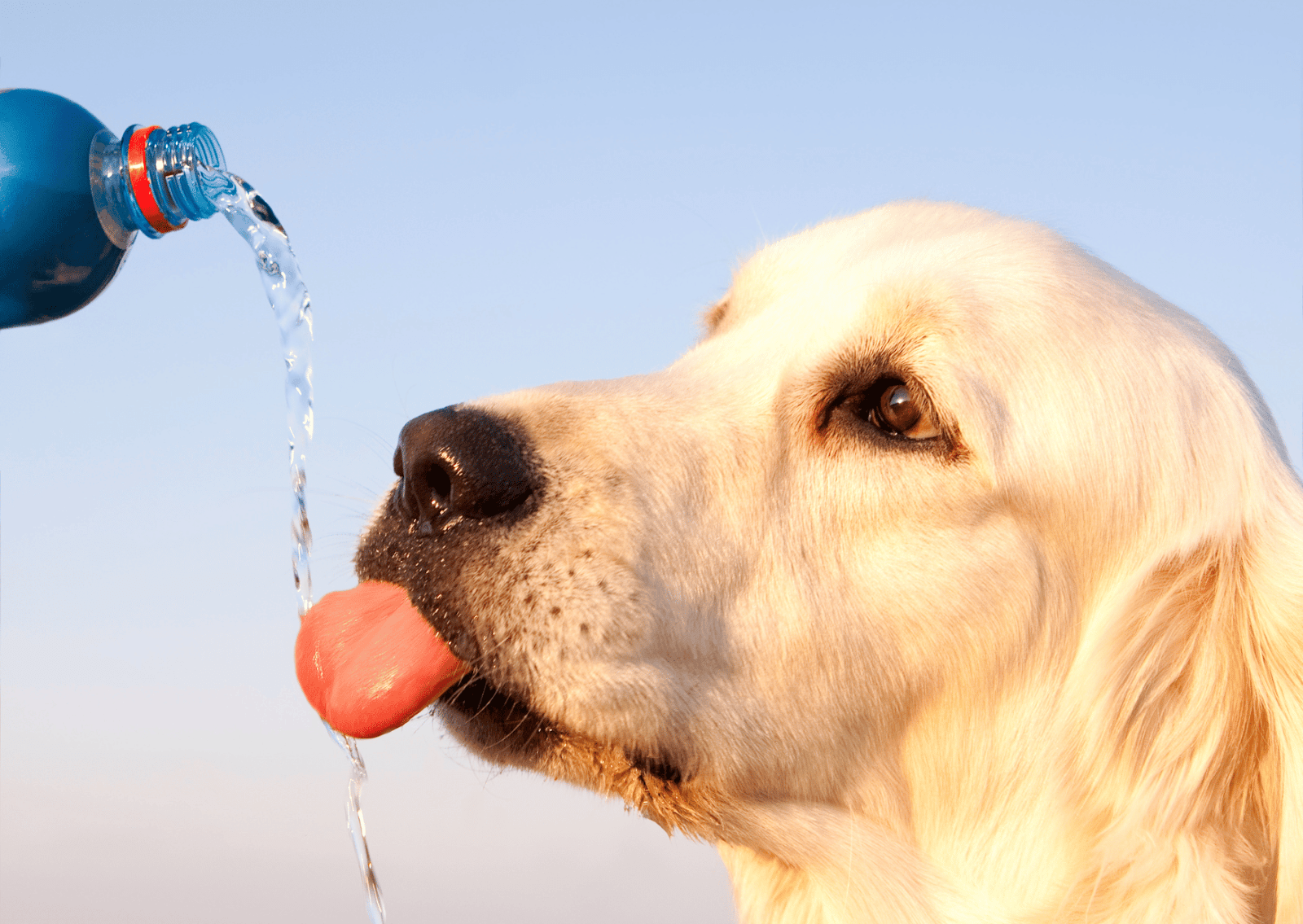
目次
犬のクッシング症候群とは?
クッシング症候群とは、副腎から分泌される副腎皮質ホルモン(主にコルチゾール)が、何らかの原因で過剰になることで起こる病気です。
別名「副腎皮質機能亢進症」とも呼ばれています。
コルチゾールは、ストレスへの対処や代謝・免疫機能の調整など、体のさまざまな働きに関わる大切なホルモンです。
しかし、これが必要以上に分泌され続けると、全身に悪影響を及ぼすようになります。
クッシング症候群は、じわじわと進行し、気づきにくいのが特徴です。しかし放置をすると内臓・皮膚・筋肉・免疫機能などにも影響が及び、犬たちの生活の質(QOL)が大きく損なわれる恐れがあるのです。
よく見られる症状
クッシング症候群の症状はさまざまで、初期にはとても気づきにくいことがあります。
以下は副腎皮質ホルモンが過剰に分泌されることによって引き起こされる初期症状です。
・水をよく飲む(多飲)
・尿の量が多くなる(多尿)
・食欲が異常に増す(過食)
・お腹が膨らんでくる(腹部膨満)
・毛が薄くなる、または脱毛が進む
・皮膚が薄くなり、傷が治りにくくなる
・筋肉量が減り、全体的に筋力が低下する
<見逃しがちなサイン>
特に「水をたくさん飲む」という行動は、比較的早い段階で現れやすいサインですが、「暑いからかな」「年齢のせいかも」と見過ごされてしまうことが少なくありません。
また「お腹がぽっこりと膨らんで見える」のは、内臓脂肪の蓄積や腹筋の萎縮が原因で、病気が進行している可能性を示す重要な兆候です。
■犬の水分摂取についてはこちらで解説しています
■犬の肥満についてはこちらで解説しています
原因と発症の仕組み
クッシング症候群には大きく分けて、以下の3つの原因があります。
◆下垂体性クッシング(最も多いタイプ)
脳の下垂体に腫瘍ができ、副腎を刺激するホルモン(ACTH)が過剰に分泌されることで、副腎からコルチゾールが出すぎてしまうタイプです。
犬のクッシング症候群の約80〜85%を占めます。
◆副腎性クッシング
副腎そのものに腫瘍(良性または悪性)ができ、コルチゾールが過剰に分泌されるタイプです。全体の10〜15%程度とされています。
場合によっては外科手術が必要になることもあります。
◆医原性クッシング
ステロイド薬(内服や外用)を長期間使用したことで、体内のコルチゾールが過剰になるケースです。
病気によるものではないため、薬の中止や調整によって改善が期待できることがあります。
動物病院でおこなう検査
クッシング症候群の診断には、複数の検査を組み合わせて慎重に検討する必要があります。
一度の検査だけで診断を確定することは難しく、段階的な判断が大切です。
まず、血液検査で肝酵素(ALP)の上昇や、血糖値・脂質の異常を確認し、体に現れている変化を把握します。
ホルモン検査は、副腎がホルモンにどのように反応しているかを調べるもので、ACTH刺激試験や低用量デキサメタゾン抑制試験などが代表的です。
さらに、画像検査(エコーやCTなど)で副腎や下垂体に腫瘍がないかを確認します。
より詳細な診断や経過観察が必要な場合には、大学病院や二次診療施設での検査を含め、継続的なモニタリングが重要になります。
治療法と継続管理
クッシング症候群は、長期間にわたって向き合っていく必要がある慢性疾患です。
治療の目的は、ホルモンバランスを整えながら薬の副作用を抑え、犬が快適に過ごせる状態を保つことにあります。
<内科的治療(薬によるコントロール)>
副腎からのコルチゾール分泌を抑える薬(トリロスタンなど)を用いて治療を施します。
通常は少量から投与を始め、定期的な血液検査で効果や副作用を確認しながら調整していきます。
治療を継続することで、毛並みや皮膚の状態が改善するケースも多く見られます。
◆トリロスタン内服に伴うネルソン症候群の可能性
下垂体性クッシング症候群の犬に、トリロスタンというお薬を長く使っていると、ごくまれに「ネルソン症候群」という状態になることがあります。
これは、お薬の効果によってACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が過剰に分泌されることで、脳の下垂体にある腫瘍が大きくなってしまうことがある、というものです。
症状が出る前に気づけるよう、定期的にホルモンの検査や画像検査(CTなど)をおこない、下垂体の大きさをチェックすることが大切です。
■犬のホルモン検査(モニタリング)についてはこちらで解説しています
<外科的治療(副腎腫瘍の摘出)>
副腎性クッシングで、腫瘍が片側に限局している場合には、副腎の摘出手術が選択肢となることもあります。
ただし、麻酔や術後管理のリスクがあるため、年齢や全身状態を考慮した慎重な判断が必要です。
◆外科治療後の副腎クリーゼのリスクについて
副腎の手術で片方を摘出したあと、もう片方の副腎がすぐにうまく働かず「副腎クリーゼ(急性副腎不全)」という命にかかわる状態になることがあります。
突然ぐったりしたり、食欲がなくなる、嘔吐するなどの症状が急に表れることもあるため、術後はペットの様子をしっかり観察してあげてください。
また、動物病院では、術後にステロイドによるホルモン補充や入院での慎重な管理をおこなうため、安心して回復を見守っていただけます。
<継続的なモニタリングと再評価>
このように治療中は、ホルモン検査や血液検査を定期的におこないながら、薬の量や効果を評価・調整していきます。
また、飼い主様による日々の観察と記録(体重・飲水量・食欲・排尿の変化など)も、治療の大切な指標となります。
クッシング症候群に対しては、飼い主様と動物病院が協力して進める“継続的なパートナーシップ”が欠かせません。
まとめ
クッシング症候群は、見た目や行動のちょっとした変化から始まり、気づいたときには進行していることもあります。
「高齢のせいかな?」と思っていた症状が、実はホルモンの病気だったというケースも少なくありません。
水の飲み方や体型、毛並みなどに違和感がある場合は、早めに健康チェックを受けることが大切です。
当院では、クッシング症候群をはじめとした内分泌疾患に対して、ホルモン検査や継続的なサポート体制を整えております。気になる変化があれば、お気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらです
・どんな変化があるの?|犬と猫の老化のサインとは
・犬の副腎摘出手術とは?|副腎腫瘍の症状から術後管理まで獣医師が詳しく説明
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。