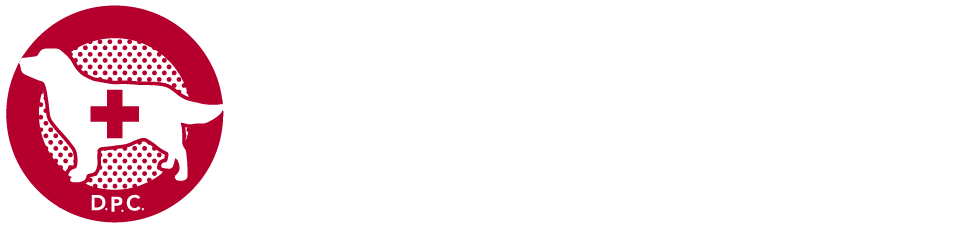秋冬に多発!猫のおしっこが出ない原因とは?緊急時の受診目安
寒くなる秋冬は、猫の「おしっこが出ない」という異変で動物病院を受診される飼い主様が増える時期です。
「少し様子を見よう」と思われるかもしれませんが、尿が出ない状態は命に関わる緊急事態。放置すると24時間以内に危険な状態に陥ることもあります。
この季節は、寒さや水分摂取量の減少、活動量の低下などが重なり、泌尿器トラブルが起きやすくなります。
今回は猫のおしっこトラブルの主な原因や見逃せないサイン、治療法、日常で心がけたい対策について、獣医師の視点から丁寧に解説します。

目次
猫のおしっこが出ない危険性
完全な尿路閉塞(尿路が詰まってしまい、おしっこが完全に出ない状態)は、猫にとって非常に危険な状態です。
腎臓から膀胱にかけての尿の流れがせき止められ、体内に毒素(尿毒素)が急速に溜まり始めます。数時間~1日で、腎不全・心不全・意識障害・痙攣といった症状に進行することもあり、緊急処置が遅れると命に関わります。
とくに雄猫では、雌猫に比べて尿道が細く詰まりやすいという解剖学的な特徴から、発症頻度も重症度も高い傾向にあります。
「明日まで様子を見てから……」「まだ大丈夫そうだし……」では取り返しがつかないこともあるため、早期受診の判断が命を守る最大のカギになります。
すぐに病院へ行くべきサイン
次のようなサインが見られた場合は、迷わず動物病院を受診してください。
これらの行動は、「痛み」や「不快感」、あるいは「排尿困難」を訴えているサインであることが多く、放置すると症状が急激に悪化する恐れがあります。
・何度もトイレに行くが、ほとんど排尿できていない
・トイレでうずくまり、苦しそうに鳴く
・トイレ以外の場所で排尿する(粗相・異常行動)
・おしっこのにおいが強い、血尿が見られる
・食欲がない、元気がなく動かない
・陰部やお腹を頻繁に舐める
かかりつけの病院が休診中や夜間であれば、お近くの夜間救急病院などに連絡しましょう。
ダイゴペットクリニックでは、豊田中央医療センターにて夜間救急診療も対応しています。
猫のおしっこが出なくなる原因
猫の泌尿器トラブルにはさまざまな原因がありますが、とくに多く見られるのは次の3つです。
◆膀胱炎や尿石症
膀胱内に炎症が起こる膀胱炎や、尿中のミネラル成分が結晶化して尿道を詰まらせる尿石症(ストルバイト結石・シュウ酸カルシウム結石など)が、代表的な原因です。
炎症や結晶により尿道が狭くなり、スムーズに排尿できなくなることがあります。
◆食事内容と水分摂取量
マグネシウムやリンなどのミネラルバランスが偏ったフードや、水分摂取量が少ない状態が続くと、尿が濃くなり、結晶や炎症が起こりやすくなります。
とくにドライフード中心の食事や、ふだんからあまり水を飲まない猫は注意が必要です。
◆ストレス
引っ越し、来客、猫同士のトラブルなど環境の変化がストレスとなり、自律神経が乱れたり免疫力が低下したりすることで膀胱炎を引き起こすことがあります。
このような原因がはっきりしない膀胱炎は「特発性膀胱炎」と呼ばれ、若い猫によく見られます。
動物病院における診断と治療の流れ
猫が「おしっこが出ない」状態で来院された場合、まず身体検査と触診により、膀胱の張り具合や痛みの有無を確認します。
その後、必要に応じて以下のような検査をおこないます。
・尿検査(比重、pH、血尿、結晶などの確認)
・超音波検査(膀胱内の結晶・結石・腫瘍などの有無を評価)
・X線検査(結石の位置・大きさ・数を確認)
・血液検査(腎機能、電解質バランス、全身状態のチェック)
一般的な治療では、まずカテーテルを挿入して尿道の閉塞を解除し、膀胱内にたまった尿を排出します。
そうして点滴によって尿毒素を体外へ排出し、脱水や電解質の異常を整えます。
状況に応じて、鎮痛剤・抗炎症薬・抗生物質などの薬を併用するほか、再発を防ぐための食事療法や生活環境の見直しも重要です。
家庭でできる予防と日常のケア
猫の泌尿器トラブルを防ぐためには、毎日の生活の中でできるちょっとした工夫がとても大切です。ここではご家庭で実践しやすいケアのポイントをご紹介します。
<水分摂取を増やす工夫>
水分をしっかり摂ることは、尿を薄めて結晶や炎症を防ぐうえでとても重要です。
・複数の水飲み場を設ける(設置場所を変える、陶器の器にするのも効果的)
・自動給水機を使って流水に興味を持たせる
・ウェットフードを取り入れる(ドライフードより水分が豊富)
・ドライフードにぬるま湯をかけて、少しふやかして与える
<トイレ環境の見直し>
猫はトイレ環境にとても敏感です。不快感があると排尿を我慢してしまうこともあるため、見直しが必要です。
・猫の頭数+1個以上のトイレを用意する
・猫砂の種類やにおい、清潔さに配慮する
・静かで落ち着ける場所にトイレを設置する
・定期的にトイレ本体の丸洗いや砂の全交換をおこなう
<ストレスケア>
精神的なストレスも泌尿器トラブルの一因になります。猫が安心して過ごせる環境づくりを心がけましょう。
・急な模様替えや来客など、環境の大きな変化を避ける
・上下運動ができるキャットタワーや隠れ家を設置する
・他の猫や人との距離感に配慮し、ストレスを軽減する
・毎日の遊びやスキンシップで心の安定をサポートする
これらの日常的なケアを通じて、猫の泌尿器の健康を守る土台をつくることができます。
特に体質的に泌尿器トラブルを起こしやすい猫では、こうした小さな積み重ねが大きな予防につながります。
まとめ
秋冬は泌尿器疾患が多発するシーズンです。気温が下がり、水を飲む量が減る季節こそ、日頃の観察と早めの対応が、猫の命を守ることにつながります。
猫の体調に「いつもと違うかも」と感じたら、それは飼い主様だからこそ気づけた大切なサインかもしれません。迷ったときは、「まずは相談してみる」ことが、ペットの健康を守る第一歩になります。
当院では、泌尿器疾患に対する緊急対応体制を整えております。いつでも、どんな小さな心配でも、お気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらです
・犬と猫の尿検査について|尿検査でわかること
・自宅でできる犬と猫の採尿方法|愛犬・愛猫の健康を守る
・猫の粗相って対策できるの?|原因や対処法も解説
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。