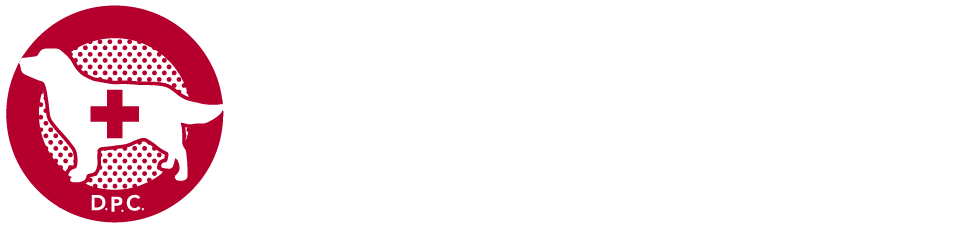犬や猫の夜鳴きの原因とは?|獣医師が解説する対策と予防法
犬や猫の夜鳴きに悩まされている飼い主様も多いのではないでしょうか。夜鳴きは、飼い主様の大切な睡眠時間を妨げてしまうだけでなく、愛犬や愛猫にとってもストレスや健康上の問題が潜んでいるサインかもしれません。
さらに、鳴き声が続くとご近所の方にご迷惑をおかけすることにもつながります。
こうした状況を防ぐためにも、夜鳴きの原因をしっかりと理解し、適切な対策を取ることが大切です。
今回は、犬や猫の夜鳴きについて、その原因と具体的な解決方法を獣医師の視点からわかりやすく解説いたします。

目次
夜鳴きとは?その特徴と注意点
夜鳴きとは、夜間に犬や猫が繰り返し鳴く行動のことを指します。この行動は、年齢や状況によってさまざまな原因で起こります。
特に子犬や子猫の時期に多く見られますが、成犬や成猫、高齢期(シニア期)でも起こることがあります。
通常、健康な犬や猫の鳴き声は短時間で収まることが多いですが、長時間鳴き続けたり、いつもと違うトーンや音量で鳴いたりする場合は注意が必要です。
体調不良やストレス、環境の変化が原因となっている可能性があるため、早めに対応しましょう。
また、高齢期には認知機能不全症候群(いわゆる認知症)が原因で夜鳴きが続くこともあります。このような場合は、早めに原因を探り、適切な対策を取ることが大切です。
夜鳴きの主な原因
<身体的な原因>
病気や痛み、加齢による視力や聴力の低下が夜鳴きを引き起こすことがあります。
特にシニア期の犬や猫では、関節炎や認知症といった加齢に伴う症状が原因となることが少なくありません。
<心理的な原因>
分離不安やストレス、寂しさなどの心理的要因も夜鳴きの原因として挙げられます。また、「鳴くと飼い主様が来てくれる」という学習が習慣化し、夜鳴きが続いてしまうケースもあります。
<環境的な原因>
引っ越しや新しい家族が増えた場合など、環境の変化が夜鳴きの原因になることがあります。また、車の振動、雨風、雷といった外部からの音や光、振動が刺激となり、夜鳴きを引き起こすこともあります。
夜鳴きの対策と予防
夜鳴きを改善するには、原因に応じた適切な対策を取ることが大切です。また、日常生活の中で予防に取り組むことで、夜鳴きを未然に防ぐことができます。
<原因別の対策と予防法>
・身体的な原因への対応
病気や痛みが原因の場合は、獣医師の診察を受けて適切な治療を行いましょう。特にシニア期の犬や猫では、定期的な健康チェックが重要です。認知症が疑われるようであれば早期の治療介入による進行予防、認知機能維持が望ましいとされています。当院では認知機能の健康維持に利用可能なサプリメントとしてトライザ、アンチノールプラスをおすすめしています。
トライザについてはこちら
アンチノールプラスについてはこちら
・心理的な原因への対応
分離不安やストレスが原因の場合は、犬や猫が安心できる環境を整え、日中に適度な運動や遊びを取り入れることが大切です。
さらに、夜鳴きをしても過度に反応せず、決して構わないようにしましょう。鳴くことで飼い主様の注目を引けると学習してしまい、夜鳴きが習慣化する恐れがあります。
・環境的な原因への対応
引っ越しや外部の刺激が原因の場合は、静かで快適な寝床を用意し、音や光などの刺激を遮る工夫をしましょう。
<日常のケアで気をつけたいこと>
・生活リズムを整える
日中は活動的に過ごし、夕方から夜にかけてはリラックスできる環境を整えましょう。
寝る前には軽い運動や遊びを取り入れ、適度にエネルギーを発散させることがポイントです。ただし、激しい運動は避け、穏やかに過ごせるよう心がけることが大切です。
・安心感を与える
愛犬や愛猫が安心して過ごせるよう、お気に入りのおもちゃや毛布を寝床に置くと効果的です。
もし分離不安が原因で夜鳴きが起こっている場合は、一人で過ごす時間を少しずつ増やし、徐々に自立を促す練習を行うことが大切です。この方法を続けることで、愛犬や愛猫が自分の空間で安心できるようになります。
獣医師に相談すべき場合
以下のような状況が見られた場合は、獣医師への相談を検討しましょう。
・突然夜鳴きをするようになった場合
・夜鳴きに加えて、食欲不振や元気がないなどの異常な症状が見られる場合
・長期間にわたり夜鳴きが続いている場合
行動診療を専門とする獣医師に相談すれば、原因を詳しく調べてもらい、適切な対策を提案してもらえます。必要に応じて、療法食や薬、サプリメント、専門的なトレーニングといった方法を取り入れることも可能です。
まとめ
夜鳴きは、単なるわがままではなく、身体的、心理的、環境的な要因が複雑に絡み合って起こる問題です。
そのため、原因をしっかり見極め、獣医師のアドバイスを参考にしながら、愛情を持って根気よく対策を続けることが大切です。
夜間に眠れない状況が続くと、飼い主様の生活にも大きな負担となります。愛犬や愛猫と快適に過ごすためにも、夜鳴きの改善に向けた取り組みを始めてみましょう。
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。