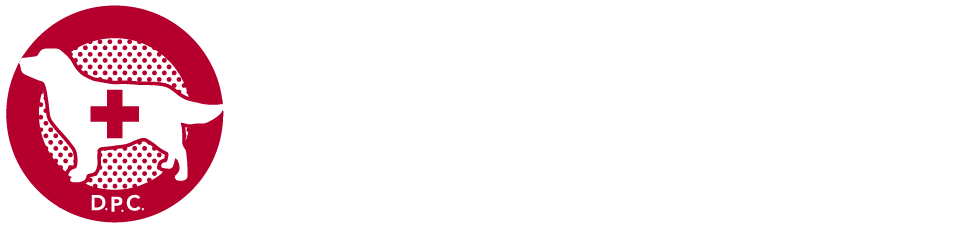避妊していない犬に多い卵巣腫瘍とは?|早期発見のポイントと治療法
卵巣腫瘍は、特に中高齢で避妊手術を受けていない犬に見られることの多い病気です。初期の段階ではほとんど症状が現れず、気づきにくいことがあるため注意が必要です。
しかし、病気が進行すると、お腹がふくらんできたり、ホルモンの異常による体調の変化が見られたりすることもあります。
そのため、日常のちょっとした変化を見逃さず、愛犬の様子をこまめに観察することが大切です。定期的に動物病院で健康診断を受けることで、目に見えない病気を早期に見つけられる可能性も高まります。
今回は、犬の卵巣腫瘍について基本的な知識をわかりやすくご紹介しながら、早期発見のために知っておきたいポイント、そして治療にはどのような選択肢があるのかを解説していきます。

目次
犬の卵巣腫瘍とは?
卵巣は雌の生殖器の一つで、性ホルモンを分泌したり、卵子を作り出したりする役割があります。
この卵巣に腫瘍ができることを「卵巣腫瘍」と呼びます。犬や猫で見られる卵巣腫瘍の中では、「顆粒膜細胞腫(かりゅうまくさいぼうしゅ)」というタイプが多いといわれています。
ただ、最近では若いうちに避妊手術を受ける犬が増えてきたこともあり、卵巣腫瘍の発症は以前と比べて少なくなってきています。
顆粒膜細胞腫は、良性のこともあれば悪性の場合もあり、外から見ただけでは判断が難しい腫瘍です。そのため、正確な診断には詳しく調べる必要があります。
また、他の腫瘍と同じく中高齢の犬に発症しやすいという特徴があります。特に、避妊手術を受けていない犬では卵巣がそのまま残っているため、卵巣腫瘍のリスクが高くなると考えられています。
気づきにくい初期症状と、進行した場合に見られるサイン
犬の卵巣腫瘍は初期の段階ではほとんど症状が現れないことが多く、気づきにくいという特徴があります。
そのため、飼い主様が異変に気づいたときには、すでにある程度進行しているケースも少なくありません。
ただ、まったくサインがないわけではありません。たとえば、いつもより元気がなかったり、食欲が落ちていたり、なんとなくぐったりしているような様子が見られたら、体の中で何かが起きているサインかもしれません。
さらに、卵巣腫瘍は大きくなるものもあり、進行するとお腹が張ってくることがあります。動物病院での触診で腫瘍が確認されることもあれば、腹水(お腹に水がたまる状態)によってお腹がパンパンにふくらんでしまい、見た目で気づく場合もあります。
また、卵巣はホルモンの分泌に関わる器官ですので、腫瘍によってホルモンバランスが乱れると、以下のような性ホルモンに関連する症状が現れることもあります。
・外陰部が腫れてくる
・発情周期が不規則になる
・毛が抜けやすくなる
・発情のような行動が長く続く
さらに、悪性の卵巣腫瘍の場合には、リンパ節や肺などの別の部位に転移してしまうこともあります。肺への転移が起きると呼吸が苦しそうになるなど、まったく別の病気のように見えてしまう場合もあり、注意が必要です。
このように、卵巣腫瘍は見た目だけではわかりづらいこともあるため、日頃の様子の変化に敏感になり、少しでも気になる症状があれば早めに動物病院で診てもらうことが大切です。
診断方法と検査について
まずは、愛犬がこれまでに避妊手術を受けているかどうかを確認する「問診」から診察が始まります。
避妊手術を受けている場合は、卵巣や子宮といった生殖器に関する病気のリスクが低くなるため、卵巣腫瘍の可能性も比較的少ないと考えられます。
一方で、未避妊の犬の場合は、卵巣が残っていることから卵巣腫瘍を含む生殖器の病気のリスクがあるため、より慎重な判断が求められます。
また、腫瘍がある程度の大きさになっている場合には、お腹にやさしく触る「触診」によって、しこりのようなものが確認できることもあります。
その後、以下のような検査を進めていきます。
・血液検査:体内の炎症の有無や全身の健康状態を確認します。
・超音波検査:卵巣やその周りの組織を観察します。腫瘍の大きさや状態が詳しくわかります。
・X線検査:転移の有無や腫瘍の大きさをチェックします。
・組織検査:確定診断を下すためには、手術で摘出した腫瘍の一部を検査機関に提出して、組織や細胞の状態を検査してもらいます。これにより、腫瘍が良性か悪性かを正確に判断することができます。
愛犬への負担をできるだけ軽くするためにも、できるだけ早い段階での診断と治療が大切です。
もし少しでも気になる様子がある場合は、無麻酔でできる超音波検査や血液検査など、体への負担が少ない検査から始めてみるのも一つの方法です。
治療法とその選択肢
犬の卵巣腫瘍に対しては、基本的に外科手術(卵巣摘出術)が治療の中心となります。
腫瘍が卵巣の中にとどまっていて、他の臓器や組織に広がっていない場合には、手術のみで治療が完了するケースも多く見られます。
しかし、腫瘍の悪性度が高い場合や、腫瘍細胞が周囲の組織やリンパ節に転移しているようなケースでは、手術後に化学療法(抗がん剤治療)を併用する必要が出てくることもあります。
また、愛犬が高齢の場合や持病などで全身麻酔に耐えられないと判断される場合には、積極的な治療ではなく、緩和ケアという選択肢をとることもあります。
この場合は、痛みや不快感をやわらげるために、鎮痛薬などを使いながら、できる限り穏やかに日常を過ごせるようにサポートしていきます。
どの治療を選ぶかは、愛犬の年齢や体の状態、腫瘍の進行具合、そして飼い主様のお気持ちなどを総合的に考慮して決めていくことが大切です。
不安なことや気になる点があれば、遠慮なく獣医師に相談しながら、一緒に最善の方法を見つけていきましょう。
術後のケアと予後について
術後は今までと同じような暮らしができますが、再発や転移の可能性を早期に見つけるためにも、定期的に動物病院での経過観察が必要になります。
卵巣腫瘍の予後(術後の経過)は、腫瘍が良性か悪性かによって異なります。
一般的には、良性の腫瘍であれば、手術後の経過は良好で再発の心配も少ないとされています。
一方で、悪性の場合は再発や他の臓器への転移が起こりやすい傾向があるため、より注意深く見守っていく必要があります。
術後には、組織検査(病理検査)の結果が届きます。この結果をもとに、今後どのようなケアが必要か、獣医師と一緒に確認していきましょう。
日常生活では、以下のようなことを意識して過ごしていただくと安心です。
・バランスの取れた栄養価の高いフードを与える
・無理のない運動と、十分な休息をとる
・ストレスの少ない穏やかな環境を整える
愛犬の様子にいつもと違う点が見られたときには、些細なことでも構いませんので、早めに動物病院へご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
犬の卵巣腫瘍は、特に避妊手術を受けていない中高齢の犬で発症リスクが高くなる病気です。
早期発見・早期治療がカギになるので、ご家庭では異変がないかをよく観察していただくとともに、定期的な健康診断で健康管理に努めましょう。
また、卵巣腫瘍は避妊手術によって予防できる可能性がある病気でもあります。
もし繁殖の予定がない場合は、若いうちに避妊手術を検討することも選択肢のひとつです。手術によって病気のリスクを減らし、安心して日々を過ごせるようになります。
愛犬の健康に関して気になることがありましたら、いつでも当院までお気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
・犬と猫の子宮蓄膿症について
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。