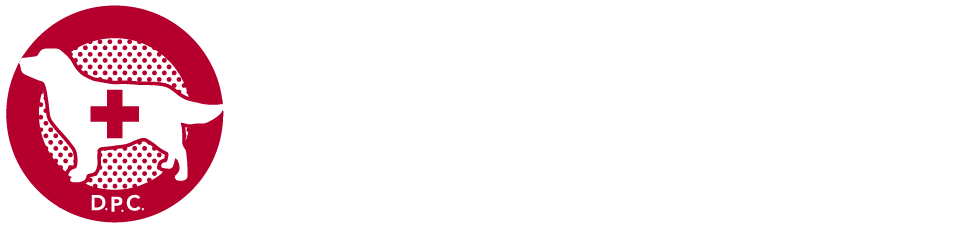【初めて犬を迎える飼い主様へ】子犬のしつけの基本|問題行動を防ぐためのコツと避けたい方法
「しつけ」と聞くと、「ちゃんとできるか不安」「全然言うことを聞いてくれなかったらどうしよう」と、心配になる飼い主様もいらっしゃるかもしれません。
たしかに難しそうなイメージを持たれることもありますが、実はしつけは“愛犬との信頼関係を築くためのコミュニケーション”です。
そして、こうしたトレーニングは科学的な根拠に基づいて行うことで、より効果的になります。
特に子犬の時期は、心や行動のベースが形づくられるとても大切な時期であり、そのタイミングでしっかりと向き合うことで、成長した後の性格や日常の行動にも良い影響を与えると言われています。
今回は、初めて犬を迎える飼い主様に向けて、子犬の成長に合ったしつけのポイントや心構え、そして注意しておきたいNG行動について解説します。

目次
子犬のしつけを始めるタイミングと心の準備
子犬のしつけをスタートするうえで、まず知っておきたいのが「脳の発達」との関係です。
犬には「社会化期」と呼ばれる大切な時期があり、一般的には生後2~3カ月頃がそれにあたります。この時期は脳が急速に発達し、外の世界からさまざまなことを柔軟に吸収できるため、しつけを始める絶好のタイミングといえるでしょう。
また、しつけを行ううえで大切なのは、愛犬の性格をよく理解することです。
犬は人との関わりをとても大切にする動物ですので、日々のふれ合いや声かけ、ご褒美(おやつやなでなで)といったポジティブな関わりが、学習を進めるうえでの大きな助けになります。
とはいえ、「こうしてほしい」「こうなってほしい」といった過度な期待を押しつけてしまうと、かえってうまくいかないこともあります。
愛犬にも一頭一頭それぞれの個性がありますので、発達段階や性格に合わせて少しずつステップを踏んでトレーニングしていくことが大切です。
今日から始める子犬のしつけ|トイレ・お散歩・困った行動への対処法
子犬のしつけをするうえで、まず覚えておきたいのが「正の強化(ポジティブ・リインフォースメント)」という方法です。
これは、愛犬が良い行動をしたときに「うれしいこと(=ご褒美)」を与えて、その行動を定着させていくトレーニングのことです。
<トイレは「成功体験」で覚えるもの>
トイレで上手に排泄できたときには、すぐにたくさん褒めてあげたり、おやつをあげたりしましょう。そうすることで愛犬は、「トイレで排泄すると、いいことが起きる」と学んでいきます。
もし失敗してしまっても叱らずに、静かに片付けるのがポイントです。
<おすわり・まて・ふせは毎日の積み重ね>
次に取り組みたいのが、「おすわり」「まて」「ふせ」などの基本的な指示です。これらは日常生活の中はもちろん、外出時やもしものときにもとても役立ちます。
指示の言葉は、ご家族全員で統一するようにしましょう。言葉がバラバラだと、犬が混乱してしまうことがあります。
<お散歩デビューはマナーも一緒に>
さらに、子犬にとって欠かせないのが毎日のお散歩です。
お散歩の際は、愛犬に合ったサイズの首輪をつけ、リードは短めに持ちましょう。特に子犬の時期は好奇心が旺盛で、思わぬ方向へ走り出すこともあります。安全にコントロールするためにも、リードの扱いには注意が必要です。
また、お散歩中のマナーとして、排泄物をきちんと処理するための袋や、尿をした場所にかけるお水も忘れずに持っていきましょう。
<噛み癖・吠え癖は子犬のうちに対応>
ここまでご紹介したのは、しつけの基本的なステップです。
ただ、順調に進んでいるように見えても、ある日突然、困った行動が見られることもあります。特に多いのが「噛み癖」や「吠え癖」です。
幼いうちは「可愛いな」と思うような行動も、成犬になるとトラブルにつながる可能性があります。
吠える声が近所迷惑になったり、噛む行動が人や他の犬を傷つけてしまったりすることもあるため、こうした行動は子犬のうちからしっかり対応しておくことが大切です。
噛み癖や吠え癖をやめさせるには、まず飼い主様が過剰に反応しないことがポイントです。そして、興奮している場合は気持ちを落ち着かせ、「おすわり」などの指示で他の行動に誘導してあげましょう。
日頃からこうした対応を繰り返すことで、少しずつ落ち着いた行動を覚えていってくれます。
NGなしつけ方法と避けるべき行動
これまで、子犬との信頼関係を育むためのしつけ方法についてご紹介してきましたが、実はその反対に、しつけの効果を損なったり、愛犬にストレスを与えたりしてしまう方法もあります。
ここでは、避けた方がよい行動や考え方についてご紹介します。
◆NG行動①:体罰や怒鳴るなどの否定的なしつけ
怒鳴ったり叩いたりするような行動は、「正の罰」と呼ばれる方法で、犬に恐怖や不安を与えてしまいます。
こうしたしつけを続けると、愛犬は「また怒られるかもしれない」と常に怯えるようになってしまう可能性があります。
場合によっては、攻撃的な行動に出たり、飼い主様の言うことを聞かなくなったりすることもあるため、体罰や威圧的な態度は避けましょう。
◆NG行動②:一貫性のない指示や対応
たとえば、「おすわり」「座れ」「Wait」など、同じ行動に対して複数の言葉を使ってしまうと、犬はどれが正しいのかわからなくなってしまいます。
しつけの基本は「わかりやすく」「一貫性をもって伝えること」です。ご家族全員で指示の言葉を統一するようにしましょう。
◆NG行動③:過度な期待や人間の基準で評価すること
犬にも一頭一頭、性格や成長のスピードに違いがあります。
「すぐにできるはず」「他の子はもうできているのに」といった期待を持ちすぎると、飼い主様ご自身も焦ってしまい、愛犬にもプレッシャーを与えてしまうかもしれません。
大切なのは、愛犬らしさを受け入れて、のびのびと成長できるように見守っていく姿勢です。
◆NG行動④:タイミングを逃した褒め方・叱り方
犬は「今この瞬間に起きたこと」と「褒められた・叱られたこと」を結び付けて学習します。
そのため、行動から時間がたってから褒めても、「なぜ褒められているのか」がわからなくなってしまいます。
正しく行動できたときには、できるだけすぐに褒めてあげるようにしましょう。
年齢に応じたしつけの進め方と目標設定
子犬のしつけは、月齢や成長段階によって取り組む内容や目標が変わってきます。
大切なのは、愛犬の発達に合ったペースで無理なく進めていくことです。
<子犬期(生後3〜6カ月)|生活の土台をつくる時期>
この時期は、トイレトレーニングや「おすわり」「まて」などの基本的な指示を覚える、いわば「しつけの土台作り」の時期です。
また、いろいろな人や犬、音や環境に慣れる「社会化」を進めることも大切な目標になります。
好奇心が旺盛なため、甘噛みをすることもよく見られますが、この段階で適切に対応することで、成長後の問題行動を予防できます。
また、パピー教室(子犬向けのしつけ教室)に通うのもおすすめです。専門家のサポートを受けながら、他の犬とのふれ合いを通じて社会性を自然に学べます。
<青年期(生後6カ月〜1歳)|自立が始まる時期>
この時期になると身体も大きくなり、行動にも少しずつ自立心が芽生えてきます。
他の犬との遊びを通じて、ルールを学ぶことが社会性のさらなる成長につながります。
青年期は、子犬期の社会化トレーニングを継続することがとても重要です。
外の環境に慣れることで、刺激に対する不安を減らし、自信を育てることができます。
また、この時期には縄張り意識が芽生えやすくなり、吠え癖などの行動が目立ってくることもあります。感情のコントロールが難しい時期なので、落ち着いて対応していくことが求められます。
ここでご紹介した年齢の区分けは、あくまでも目安です。
実際には、犬によって成長のスピードも性格も異なります。無理に合わせようとせず、愛犬に合ったオーダーメイドのしつけを進めていきましょう。
また、子犬の成長はとても早いため、しつけの方法やタイミングに迷ったときは、獣医師やトレーナーなど専門家に相談することも大切なポイントです。
まとめ
科学的な根拠に基づいた正しいしつけは、飼い主様と愛犬との絆をより深めるだけでなく、将来的な行動トラブルを防ぐためにもとても大切です。
最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、「一貫性」「忍耐」、そしてなにより「愛情」を持って、少しずつ取り組んでいきましょう。
しつけは短期間で終わるものではなく、日々の積み重ねがとても大切です。
「なかなか指示を覚えてくれない」「吠え癖や噛み癖が気になる」といったお悩みが出てきたときは、早めに獣医師やしつけの専門家に相談してみてください。
また、ご家庭だけでの対応が難しいと感じる場合には、パピー教室の利用もおすすめです。
当院でも定期的に開催していますので、初めての方もお気軽にご参加ください。
■関連する記事はこちら
・子犬を迎えた方へ
・犬の分離不安について|原因や対処法を解説!
■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!
・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら
・岡崎大和院の病院案内ページはこちら
・日進オハナ院の病院案内ページはこちら
・名古屋名東院の病院案内ページはこちら
※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。